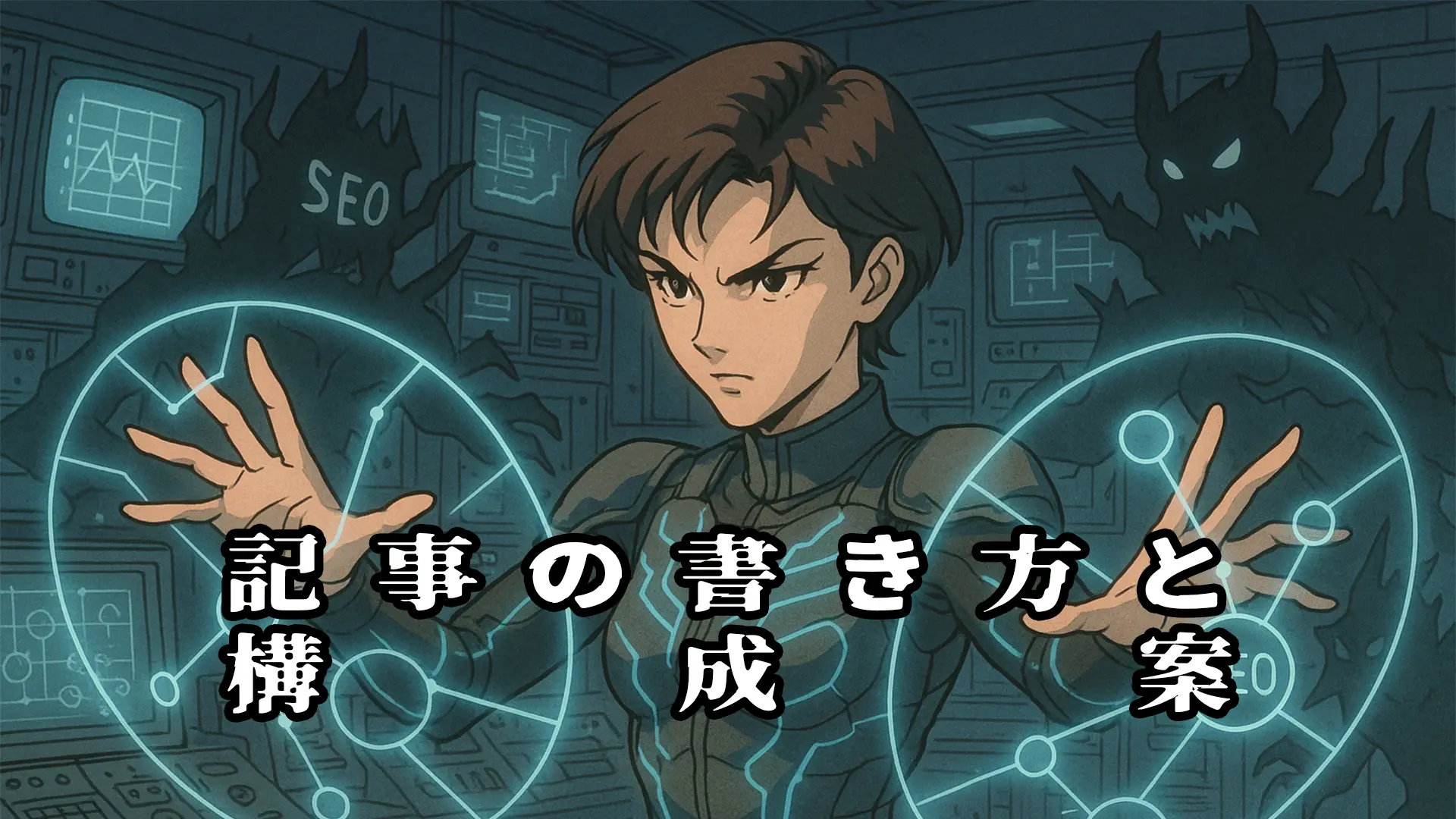はじめに|SEO記事を構成する力が、成果を左右する
「段落の順番を入れ替えただけで、CVが倍増した」
構成変更による成果向上の事例、実務の現場では珍しくありません。
SEO対策とは、記事を書くことだけではありませんが、記事の構成力は成果に直結します。
SEOにおける「構成」とは、ただ文章を並べるだけの作業ではなく、読者の行動を設計する仕事です。
検索意図にマッチした順序で情報を届けられるかどうかで、記事の価値も数字も、大きく変わります。
とくにSEOライティングを自社で初めて担当する方や、ブログをこれから立ち上げる個人の方からは、よくこんな声を聞きます。
「何を書けばいいかは決まっているのに、まとまらない」
「テンプレ通りに構成したけど、成果が出ない」
ライティングテンプレートは確かに強力な武器です。ですが、全てのコンテンツが同じ構造では、ユーザーが退屈して離脱してしまう可能性もでてきます。
特にあなたのサイトの記事を読み慣れたユーザーほど、構成のパターンに飽きやすく、ページ内のアクション率も落ちていきます。
なにより、中身のないコンテンツでは一時的に検索上位表示を獲得できても、ページ内でユーザーアクションが起きず、いつの間にか検索順位が100位圏外に落ち込むこともしばしばです。
構成とは、記事単体の成果だけでなく、サイト全体のパフォーマンスを左右する技術。
この記事では、「構成案をどう作るか」「何を判断基準にするか」について、現場目線で解説していきます。
SEO記事構成はテンプレを埋める作業?
SEOライティングを始めたばかりの方の中には、「構成とは見出しを並べること」と誤解している方が少なくありません。
なかには、「PREP法で書けばいい」「序論・本論・結論があればOK」と、型に文章を流し込むだけで成果が出ると思っている人もいます。
ですが、特にSEO対策初心者の方に注意してほしい点が、SEOにおける構成とは、テンプレートに沿って文字を埋める作業ではないということです。
構成とは、「そのテーマにおいて、ユーザーが本当に求めている情報を、どの順番で、どの深さで届けるか?」を考える作業です。
たとえば、検索キーワード「副業 おすすめ」の記事で、最初に「副業とは?」の説明が2,000文字続くような構成では、多くの読者が離脱してしまいます。
知りたいのはおすすめの副業なのに、「副業の定義」や「副業の歴史」に時間をかけられては、ユーザーの検索意図とズレてしまいます。
ユーザー目線で「届けるべき内容」を差し込む判断力
「構成案を守る」のは大事ですが、時には構成を超えて伝えるべき情報を差し込む判断が必要です。
テーマによっては、多少流れを乱してでも、「あ、それ知りたかったんだよ!」という内容を先に入れるほうが、ユーザーに刺さることもあります。
多少の野暮ったさは気にしなくても構いません。
むしろ、その人間味やあなたらしさが、親近感や信頼感につながることも多いのです。
成果指標として重視しているもの
弊社では、構成案を組む際に特に重視しているのは以下の3点です。
-
CVR(コンバージョン率)
-
成果地点に対して、構成がちゃんと読者を導けているか?
-
ゴールが「問い合わせ」や「購入」であれば、文章よりページ全体の導線設計にまで踏み込む必要があります。
-
-
検索意図と検索キーワードの合致
-
「ユーザーはこのキーワードで、何を知りたいのか?」を掘り下げて考えること。
-
そのテーマにおけるターゲットユーザーが使いそうな言葉を優先して使います。
-
-
ヒートマップ解析におけるアクション
-
「読了率」は重視していません。なぜなら、全ての記事内容を必要とするユーザーばかりではないからです。
-
ただスクロール率を含めたページ内アクションを重視しています。ページ全体をざっとでも眺めてくれたなら、それはユーザーの興味の現れです。
-
また、滞在時間が極端に短くても、ユーザーが知りたい情報を得て離脱したのなら、それは悪い結果とは限りません。
「滞在時間が短い=失敗」ではないという判断基準も大切です。
ページ構成はライティングだけの話ではない
SEOにおける構成とは、見出しや段落の配置だけで完結する話ではありません。
たとえばCTAボタン(問い合わせボタンや購入ボタン)をどこに設置するか。
ファーストビューに何を置くか。
これらも、構成の一部です。
構成案づくりとは、文章を組み立てる作業というより、「ページとしての設計図」を引く作業に近いもの。
検索意図に合致した情報を、適切な順番と深さで、かつ行動を促すように配置する。
それがSEO記事の構成です。
よく使われる構成パターンとテンプレートが通用しない場面
SEOライティングにおいて、よく使われる構成パターンには以下のようなものがあります。
-
三部構成(序論・本論・結論)
-
PREP法(結論→理由→具体例→結論)
-
起承転結
-
起承転転結(最後まで展開し続ける)
これらの型は、情報整理や草稿段階でのクオリティアップに役立つツールです。とくに構成作業に不慣れな方にとって、思考を整理するうえでは有効なガイドになります。
ただし、そのままパターンに沿って記事を埋めるだけでは失敗するケースもあります。
たとえば、構成パターンを埋めることに集中しすぎて、ページ上部と下部の結論が食い違ってしまう。
あるいは、ユーザーの検索意図に答えるべきポイントが中盤以降にしか登場しないなど、実務ではよくある構成ミスです。
構成とは、テンプレを埋める作業ではなく、ユーザーの体験を想像して、どの順番で伝えるのが最適かを考える行為です。
また、常に「型」ばかりを意識していると、テンプレートで埋めきれない話題や文脈に直面したとき、筆が止まってしまうことがあります。
実際に、誤字脱字が多く、目新しい切り口もないライターのコンテンツが、検索上位を獲得しているケースも見かけます。
それは、型通りの文章ではなく、「ユーザーが実際に体験しそうな話題」をストレートに届けられているからです。
つまり、構成パターンは「最初の土台」として活用しつつ、最終的には著者自身の感性や現場感覚を加えることが不可欠です。
良い構成案とは?判断の基準と現場での工夫
良い構成案とは何か。これはSEOライティングの現場で、常に問われるテーマです。
私が構成案の善し悪しを判断する際に最も重視するのは、「冒頭と締めに、ユーザーにどんなアクションを取ってほしいかが明確に伝わっているか」です。
記事の中身がどれだけ良くても、読者が次にどうすればいいのかわからなければ、成果にはつながりません。
「YouTubeチャンネル登録よろしく」でもいい。人は、言われなければ動きません。
また、構成自体もユーザーの体験を強く意識するべきです。
とくにスマートフォンからのアクセスが主流の今、ひと目で見通しの立つ構成は必須条件。
各段落は短く、見出しと小見出しの関係も一目で理解できるように整理します。
スマホの小さな画面で、文章がぎっしり詰まっていたら読む気をなくしてしまう人もいるでしょう。そうならないよう、構成案の時点でターゲットの趣向に合わせた視認性・可読性を設計する必要があります。
良い構成案とは、単なる「情報の順番表」ではありません。
ユーザーの行動を自然に導き、アクションを引き出す設計図であるべきです。
「構成テンプレ」は使うべきか?
「三部構成」「PREP法」「起承転結」など、文章構成のテンプレートは、確かに便利です。
とくにSEOライティングに初めて取り組む場合、構成に迷ったときの心強い味方になるでしょう。
ですが、テンプレートに頼りすぎると、記事の質は一気に平凡になってしまいます。
-
「とりあえずPREPで書けばOK」
-
「結論→理由→事例→まとめ」の順で埋めるだけ
-
他サイトにあっても不自然じゃない、おとなしい内容
これらはすべて、テンプレ構成が生む落とし穴です。
中でもよくあるのが、「テンプレ通りに並べたが、中身が薄い」ケース。
キーワードを並べて、古い情報を引用して、段落ごとの焦点も曖昧。
結果として、「誰が、なぜ書いているのか」が伝わらず、読者の心にも検索順位にも届かない文章を作ってしまいます。
テンプレは骨組み|肉付けはあなたの感性で
テンプレはあくまで骨組み。
そこに血肉を与えるのは、あなた自身の視点や経験、そして「伝えたい本音」です。
実体験を交えたり、よくある意見にあえて「NO」と言ったり。
読者にとって読み応えのあるパートは、むしろそういう部分に宿ります。
たとえば、業界で使われる専門用語やキーワードも、「本当に意味をわかって使っているか」は読者に伝わります。
関係コンテンツにしっかり目を通し、誤用のないよう注意するのも、読者への信頼を得るための大事な工程です。
雑記サイトのアクセス数が爆発的に増加|構成以前に企画で決まっていた
実際に、雑記だけで大ヒットしたサイトもあります。
そこに型はありませんでした。
なぜなら、記事の構成以前に、企画の勝利だったからです。
-
誰に向けて
-
何を面白がってもらいたいか
-
どういう切り口で届けるか
こうした構想(=企画)の段階で、すでに成功は見えていたのです。
だからこそ、テンプレにとらわれすぎて筆が止まるくらいなら、
一度型から離れて、ざっくばらんに書いてみるのも十分アリです。
良い構成案の特徴とは?スマホ時代の読者行動を意識する
「成果を生み出すSEO構成案の具体的な特徴」を整理し、スマホユーザーを前提にしたページ設計についても触れていきます。
スマホ時代の構成は読者の指の動きまで意識する
SEO記事において「構成案」とは、情報の並び順を決めるだけではありません。
それは、ユーザーの行動を設計するという視点を持つことでもあります。
とくにスマホで読むユーザーが多い今、次のような構成の工夫が重要です。
-
段落は短く、スッキリ読みやすく(画面1スクロールで1段落)
-
小見出しと段落が1対1対応で整理されている
-
ぱっと見で「自分に関係ある」と伝わる導線がある
-
ページ上部と下部のメッセージ性が一致している
「スマホで画面いっぱいに文字が詰まっていたら、読む気がなくなる」
そんな読者心理を想定することで、構成のミスや脱線も防げます。
ユーザーにしてほしいことを明確に伝える
どんなに良い記事でも、「どうしてほしいか」が書かれていなければ、読者は動きません。
構成を考えるときに意識すべきは、「冒頭と締めでユーザーにアクションを促せているか?」
-
商品購入
-
資料ダウンロード
-
メール登録
-
SNSシェア
-
YouTubeチャンネル登録
など、何でも構いませんが、言わなきゃ伝わらないのがWebの世界です。
「読者の気持ちを動かす構成」とは、行動を生み出す設計に他なりません。
成果を生む構成案のポイントまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 段落構成 | 1段落を短く・視認性重視(スマホユーザー前提) |
| 小見出し | 段落内容を的確に示すラベルとして活用 |
| アクション誘導 | 冒頭・締めで明確に呼びかける |
| メッセージ整合性 | ページ上部と下部で結論が食い違わないように |
| 離脱防止 | 長文で詰め込まない、読者の指の流れを想定する |
構成案作成の手順と実例紹介|書く前の設計が9割
構成案づくりは、書くための準備だけでなく、「成果を出すための設計図」です。
実務でよく用いる構成案の作成手順と、実際に成果につながった構成調整の実例をご紹介します。
構成案の基本ステップ(実務ベース)
以下は、自社やクライアント向けにSEOライティングを実施する際によく使う構成案作成フローです。
-
記事の目的を定義
└ CV獲得?リード獲得?認知向上? -
想定読者(ペルソナ)を明確に
└ 年齢・性別・立場・悩み・検索意図 -
キーワードと検索意図を整理
└ メインKW+サジェストKW+類義語+よくある質問 -
競合分析(上位記事の構成をチェック)
└ 構成の共通点/不足している視点を洗い出す -
見出し(H2)→小見出し(H3)を設計
└ 情報を順序立てて配置 -
CTA・CV導線をどこに入れるか設計
└ 冒頭/中腹/末尾などの位置を検討
▶ 段落の順序を入れ替えただけでCVが2倍に
ある商品LPの記事で、「段落の順番を入れ替えただけ」でCV率が約2倍に向上したケースがあります。
-
Before:商品スペックが先にくる構成
-
After:悩み共感→解決策→他者評価→スペック→導線
検索ユーザーの「今すぐなんとかしたい」という気持ちに合わせてWhy → How → Whatの構成にしたことで、明らかに行動率が変わりました。
スクロール率や滞在時間も増加し、ヒートマップ上では「離脱エリア」が消えたことを確認。
構成案づくりで意識していること(現場ルール)
-
1文目が、次の1文を読ませることがすべての起点
構成はもちろん大切だが、最終的に人を動かすのは文章の“勢い”と“引き”だと考えています。 -
細部に神が宿る意識を持つ
全体構成よりも、むしろ1段落内の論理や流れを重視することも多いです。 -
シンプルな構成案を心がける
構成はシンプルに。
あえて構成に余白を残すようにして、書きながら思いついた余談や小話を自然に差し込めるようにしすることもあります。
完成形をカッチリ決めすぎると、ライティングの余地がなくなり、熱がこもらない記事になることもあるからです。
ただ、これをやると脱線した話のほうが面白くなってしまうこともあり、作業時間が限られている場合は、おすすめしません。
構成は「設計図」だが加筆の余地も残す
テンプレートや構成案が大事なのは間違いありませんが、それに縛られすぎると、読者の心に届かない。
自分自身の感性や、「この余談、ちょっと入れたいかも」という直感も大切にしたいところです。
構成案の前にあるべき企画という視点
良い構成案を作るには、その前段階で「そもそもこの記事は誰のために書くのか?」「どんな切り口が面白いか?」といった企画視点が欠かせません。
構成が上手くいかない人の多くは、「テンプレにうまく当てはめられない」「どの順番が正解かわからない」と悩みます。
けれど実は、その前に何を伝えたいか(面白いと感じてほしいか)が明確になっていないケースがほとんどです。
たとえば、ある雑記ブログでは、「型なんかありません」と豪語する運営者が、共感されやすい生活体験やニッチな視点を徹底して企画に落とし込み、大きな成果を出していました。構成以前に、読みたくなる理由があります。
構成案は、企画の筋が通っていてこそ、初めて機能します。
ユーザーの目線で「どんな話題を、どんな見せ方で出せば刺さるか」を決める。
その方向性が明確であれば、構成で迷う場面はぐっと減ります。
SEOライティングにおける構成は、「情報の順番」だけでなく、「どんな熱量で何を届けるか」の設計でもあるのです。
当サイトはリンクフリーです。
ご自身のブログでの引用、TwitterやFacebook、Instagram、Pinterestなどで当サイトの記事URLを共有していただくのは、むしろありがたいことです。
事前連絡や事後の連絡も不要ですが、ご連絡いただければ弊社も貴社のコンテンツを紹介させていただく可能性がございます。